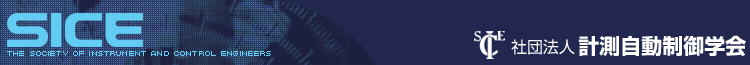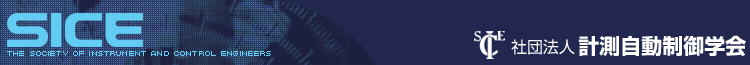| 12月16日(木) |
| 9:00~ 挨拶 |
9:10~10:40 計測制御序論(計測制御エンジニアについて)
帝京平成大学(元/計測自動制御学会会長) 江木 紀彦 君 |
| 「計装」は産業の発展の脇役としては評価されたが,本質的にどのような役割を果たしたかについては理解されていない.巨大石油プラントが殆ど無人に近い運転で安全に稼動している.「計装」あってのことである.それでこの「計装」の原点から,現代までどのように発展してきたかを解説し,これからその整合性が問題になると思われる,人の頭脳の代行を担う計装技術の実力と,人の能力との接点について考える材料を提供する. |
| (休 憩) |
| 10:55~12:25 計測制御基礎講座 東京大学 新 誠一 君 |
| 計測制御は表裏の関係である.制御には良い計測が不可欠であるし,計測はその計測値を活用しなければ意味がない.本講義では,計測と制御を連続したものととらえ,その基礎をセンシング,モデリング,コントロールの三段階に分けて解説する.実務者に理解しやすいように,家電ネットワークや自動車などの事例も交えながら分かりやすく講義する. |
| (昼食休憩) |
| 13:30~15:00 鉄鋼業の計測制御技術 川鉄電設 岩村 忠昭 君 |
| 日本の鉄鋼業は,質量ともに世界一の地位を築き上げた.これらの原動力となったものの一つに計測制御技術があり,成長期や昨今の転換期においては,まさにその推進力となっている.鉄鋼業は市販の汎用技術では解決されない課題が多く,自社技術あるいはメーカとの共同研究により厳しいニーズに対応している.まず鉄鋼業における計測制御技術の概要を俯瞰し,ついでセンサ開発状況について実例に基づいて説明する.さらに得られたセンサ情報を,具体的に実操業で如何に活用しているかについて説明する. |
| (休 憩) |
| 15:15~16:45 化学プラントの計測制御技術 名古屋工業大学 伊藤 利昭 君 |
| 計装システムが化学産業において今日まで果たしてきた役割と今後果たすべき役割を論じ,化学産業の計装システム設計の基本である自由度に基づく設計法,計装システムの中核である制御系,緊急事態回避システム,マンマシンインタフェースの設計,および計装システムを構成する機器の選定と設計について説明する. |
| ※1日目の講座終了後,技術懇談会を予定. |
| 12月17日(金) |
| 9:00~10:30 ビル空調の計測制御技術 山武ビルシステムカンパニー 神村 一幸 君 |
| ビル建設,運営の際には,快適な居住環境と省エネルギーが要求される.快適な居住環境の実現と省エネルギーは一見矛盾しているような印象を与えるが,適切な空調設備設計と計測制御システムの適用により矛盾なく実現できる.ここでは,空調計測制御の特徴である快適なオフィスの温熱・空気質環境を実現する居住環境制御,地球環境負荷低減およびビル運営費低減に貢献する省エネルギー制御,およびこれらの連携をより効果的に実現するための新しい計測制御技術の取り組みについて説明する. |
| (休 憩) |
| 10:45~12:15 制御システム基礎講座(DCSの歴史) JEMIMA:日本電気計測器工業会(前/横河電子機器(株)社長) 若狭 裕 君 |
| DCS(分散型計装制御システム)が1975年に市場に出されてから30年近くが経過した.この間DCSは計装のディジタル化を通してプロセス産業の効率化に大きく貢献した.本稿では,アナログ計装の時代から現在に至るプロセス制御システムの歴史を振り返り,マイクロプロセッサ,通信技術,ソフトウェア技術など,分散型システム・アーキテクチャが生まれた技術的背景に触れつつ,DCSの機器構成,機能構成,高信頼化の手法等について解説する. |
| (昼食休憩) |
| 13:30~15:00 自動車の計測制御技術(前半) トヨタ自動車 田中 宏明 君 |
| 「予防安全のための最新制御システムについて」:わが国における交通事故の現状をみると死亡事故こそ,ピーク時の約半分に減少したものの.死傷事故自体は未だ増加傾向にある.一方,ここ数年,最新のセンサ及び制御テクノロジーを活用した様々な安全装備が開発され,急速に市場に導入され始めてきた.交通安全のための最新システムを極力,実際の事故分析と関連付け,通常の運転状態から,事故発生に至るプロセスに対応させて紹介する.併せて,今後の交通安全システムのインテリジェント化の方向性についても言及する. |
| 自動車の計測制御技術(後半) トヨタ自動車 鯉渕 健 君 |
| 「VSC(車両安定性制御システム)の開発」:自動車の予防安全性能を飛躍的に向上させることを目的として,急なハンドル操作や路面状況の急変など,不測場面における車両横滑りを抑制し,旋回限界での車両安定性やコーストレース性を向上させる車両安定性制御システムVSC(Vehicle Stability Control)を開発した.そのコンセプト,制御理論,効果等について概説する. |
| (休 憩) |
| 15:15~16:45 製紙業の計測制御技術 王子製紙 森 芳立 君 |
| 紙パルプ製造工程の全体について説明し,その中の代表的な設備である連続蒸解釜と抄紙機の計装の概要と,そこで使われている紙パ産業の特有のセンサーの概要について説明する.さらに,簡単なアドバンスト制御を用いた連続蒸解釜の蒸解度制御,抄紙機の銘柄変更制御などの制御システム開発の取組み,そして,ミルワイドシステムと呼ばれる紙パルプ産業のCIMの取組み等についても紹介する. |